2005年度第1回全県研究会
模擬授業とシンポジウムでせまる「評論文の指導 〜国語の学力、指導過程、教材のあり方〜 」
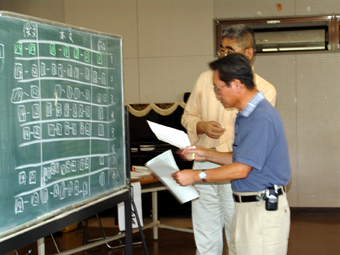
9月10日に2005年度第1回全県研究会は、模擬授業とシンポジウムで迫る「評論の指導 〜国語の学力、指導過程、教材のあり方〜」と題して、 伊那市の伊那北高校同窓会館「薫が丘会館」で35人のみなさんの参加で、開催されました。
午前中は、科学的「読み」の授業研究会会員の加藤郁夫氏(大阪柏原東高校)によ る模擬授業を体験しました。
また、午後は、加藤先生の他に、東大名誉教授の柴田義松先生と桐原書店の教科書編集局長の竹松文士氏をパネリストに迎え、国語の学力、評論文 の指導法、指導過程、教材のあり方について、論議を深めました。
35人が参加、読み研方式の模擬授業で生徒役 段落分けで喧々諤々

【模擬授業】模擬授業では、参加者が五・六人の小グループに分かれ、小学校の説明的教材「「魚の感覚」と阿部公房の「日常性の壁」を使いなが ら、読み研方式による評論・説明的文章の指導法・指導過程について学びました。読み研方式の指導過程は表層読み(①指名読み、②難語句・表現の 指導)、構造よみ、論理読み(要約読み)、吟味読みという指導過程です。構造読みの授業では、形式段落を前文、本文、後文の三つに分けることを とおして、その文章の持つ構造を明らかにします。
 論理読みでは、柱の段落・柱の文の関係を明らかにすることをとおして、より文章を詳細に理解していきます。また、吟味読みでは、その文章の説 明(論証)が適切であるかどうかの検討をします。
論理読みでは、柱の段落・柱の文の関係を明らかにすることをとおして、より文章を詳細に理解していきます。また、吟味読みでは、その文章の説 明(論証)が適切であるかどうかの検討をします。
「魚の感覚」では、鱒が八時になるとえさ場付近に集まってくる現象の解釈として、十分な検証もなく、八時の鐘の音を聞いて集まっているのだと 結論づけてけている点や、「音が聞こえる」と「音を聞き分けることができる」というレベルの異なる反応が同一に扱われている点などが指摘されま した。
阿部公房の「日常性の壁」の構造読みでは、グループ毎に段落分けが大きく分れ、なぜそこで分けたのかをめぐり、喧々諤々、グループ毎やグルー プ間で論戦が展開されました。
加藤氏も、段落がどこで分かれるかに目を奪われるのでなく、構造読みの目的は、文章内容を大きく把握していくことにあると指摘していますが、 論戦をとおして、次第に文章の構造・内容が明らかになってプロセスは見事でした。
シンポジウムで指導法、学力、教材論など、評論文の指導 様ざまな角度から論議

吟味読み・批判読みの重要性
酒井氏からは、現場での評論文の指導に際しての課題が提起されました。また、教科書の内容をきっちり教えることに重点を注いでいて、批判読 みという観点は刺激になったという感想が述べられました。
柴田先生は、特に高校の国語教師に期待したい国語の学力は、文章に含まれるものの考え方、イデオロギーを批判的に読む、批判的リテラシーの習 得だとして、そのための基礎的な能力を身につけることも大事だと述べました。

PISAの読解力調査で、日本の生徒たちの学力格差が深刻で、特に書かれた情報を自らの知識や経験に関連づける熟考・評価の問題で、無答が多 く、習熟度レベル1以下の生徒は、全体の2割から3割位。2000年調査から比べても激増していることを指摘、書いてあることを理解するだけで はなく吟味する読み方を育てていくことの大切さを強調したうえで、自分と対立する意見をぶつけ合い、より論理的かを競う「討論」の大切さを指摘 しました。
加藤氏は、読み研方式で、わからないのは必ずしも読む側の理解力のせいではなく、場合によっては文章そのものに説明の不十分さがあり、分から ないこともありなんだと思うようになり、授業がやりやすくなった。特に説明的文章は、文学的文章に比べ、生徒にとって縁遠くよくわからない。吟 味読みでどっかおかしいとこないかと批判的に読んでいくことで、生徒が主体的に関われる。次に何で分からないかを追求していけばいい。そのこと から、筆者の意見を受け、自分の考えは、どうなんだというところで、読みが読みにとどまらず、小論文として発展させていくこともできると述べま した。

評論文指導のあり方
竹山氏は、国語の学力が、他教科に比べ、あいまいで神秘的ですらあることを指摘。問題集を作成するプロセスで、それを客観化・系統化すること が出発点だったと述べました。
また、教科書編集のこだわりとして、ある種の観念を誘導する教材は、教材としては、どうなのかと、問題提起をしました。
参加者のみなさんを交えた論議では、「日常性の壁」の第二段落のように、本来分けてしまった方がいいと思う段落が一緒くたになっているような、 論理的な書き方でない評論文が教科書には多いというフロアーの指摘に対して、加藤氏は、「構造読みをとおして、むしろ生徒にそれが見えるのがよ く、批判的な読みを育てるべきだ」と答えました。
教材の問題については、竹山氏の意見はよくわかるとしながら、そうでない教材は、現実に対する批判で、わたしたちには答えづらい世界。提起さ れた問題の答えが、教科書になく、内容そのものシビアだという意見もありました。
参加者からは、「パネラーの人選が各方面の方々で有意義なお話でした」「強いて言えば時間がもっとほしい」などの感想がありました。
- 1 大西忠治「入門・科学的「読み」の授業」 明治図書(教育新書)
- 2 阿部昇「力をつける「読み」の授業」 学事出版
- 3 阿部昇「授業づくりのための「説明的文章教材」徹底批判」 明治図書
- 4 阿部昇「文章吟味力を鍛える」 明治図書
- 5 読み研運営委員会編「科学的な「読み」の授業入門」 東洋館出版
- 6 読み研 国語授業の改革1「国語科新教材の徹底分析」 学文社
- 7 読み研 国語授業の改革2「国語科新教材のポイント発問」 学文社
- 8 読み研 国語授業の改革3「この教材で基礎基本としての言語スキルを身に付ける」 学文社
- 9 読み研 国語授業の改革4「国語科の教科内容をデザインする」 学文社
- 10 読み研 国語授業の改革5「新教材の徹底研究と授業づくり」 学文社
- 11 柴田義松ほか編「あたらしい国語科指導法」 学文社
- 12 柴田義松ほか編「大学生のための日本語学習法」 学文社
